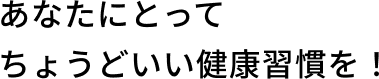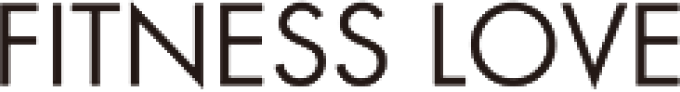30代半ばにして「伝説」と呼ばれた男がいる。昨年でデビュー35年、今年で復帰して20年を迎えた須江正尋選手である。日本一の背中と称され、ジュニア世代のビルダーたちからもリスペクトを集める彼の軌跡を振り返るとともに、そのボディビル哲学に迫った。
取材・文:藤本かずまさ 写真:徳江正之、中島康介、月刊ボディビルディング編集部
甦る 須江正尋伝説・後編
―― しかし、7 年の空白期間を経て2 0 0 2 年に復帰を果たします。2001年の3月からトレーニングを再開しました。
須江 そのきっかけをくれたのも妻でした。私がトレーニングをしていたことを妻は知っていますし、ボディビルの大会に出ていたことも知っています。でも、今はやめている。私はたまに大学に行って学生たちを指導していたのですが、そのときはすごく楽しそうにしていたみたいなんです。そんな私を見て、「何でやりたいことがあるのにやらないの」と。当時は田代(誠)選手が一気に駆け上がってきて、対抗馬として合戸(孝二)選手がいて、若い山岸(秀匡)選手や相川(浩一)選手も台頭してきていました。そういった「若い選手たちに負けるのが怖いの?」と。
そこで私も説明しました。やるとなったら今の生活には戻って来られないよと。ただ彼女は、私にはそういう人生を懸けてやりたいものがないから、そういったものがあること自体が羨ましいと。だったら彼女にどういった世界にいたのか見せてあげようという気持ちになったんです。
しかし、仕事も忙しく、ジムに行っている時間はとても作れるような状況ではありませんでした。ちょうどその頃、家を建てようという話をしていた時期だったんです。そこに6畳のトレーニングルームを作らせてもらい、トレーニングを再開しました。
――今でこそホームジムはよく聞く言葉になりましたが、当時はどうだったのでしょうか。
須江 本格的に自宅でトレーニングをして、日本選手権を目指すという人はいなかったと思います。限られた設備しかないんだったら、それを徹底的に使いこなして他の選手たちに対抗してやろうと。トレーニングの感覚自体は幸いにも残っていたので、その感覚が残っているのであれば、どこでトレーニングしても同じだと。
また、ちょうどそのとき、「鍛錬」というメーカーを知ったんです。非常にコンパクトで、面白いマシンもありました。滋賀の工場まで実際にマシンを確認しに行き、感触を確かめて購入しました。当時から使っていたラットマシンは今、ジムに設置しています。
――復帰するならその舞台は日本選手権しかなかった?
須江 そうです。やるからには最初から頂点を目指そうと。できると信じていたし、また目標を高いところに置いておかないと元いた場所には戻れないと思っていました。
――当時は1試合のみ復帰するおつもりだったんですよね。
須江 最初はそうでした。妻には一度見せればいいだろうと思っていました。でも、復帰した日本選手権で5位という成績になって、妻が「来年は勝たなきゃね」と。そこで、また出ていいのかなと思いまして(苦笑)。
――ご自宅でトレーニングすることで、トレーニングの技術力が磨かれたというのもあるのではないでしょうか。
須江 それはあるかもしれないです。自宅には背中であればラットマシンくらいしかありません。どのように使えば異なった刺激が得られるのか。それは私にとって至上命題で、いろいろ考えて工夫しながら、感覚を頼りにトレーニングを進めていました。そこで体の使い方を自在にコントロールしながら動かしていく感覚が養えたような気がします。
――また上腕二頭筋の長頭腱の断裂など、怪我も多く経験されました。
須江 それこそ身体の使い方がうまくなかったということかもしれませんし、筋肉の組成自体があまり強くなかったのかもしれません。ですが、最近はそういった怪我をすることもありません。怪我をせずに強度の高いトレーニングをしていくにはどうすればいいか、やはり考えるようにはなりました。一番大切にしているのは、無理な動作をしないということと、急激な負荷をかけないことです。
――須江選手はトレーニングを説明する際に時折「攣りそうになるほど収縮させる」という表現を用います。
須江 高重量を扱えるうちはいいのですが、未来永劫重量が伸び続けていくわけではありませんから、いつか頭打ちします。これは軽い重量を使いこなしていくためのテクニックです。
ネガティブを大切にしたいという気持ちは皆さんお持ちだと思うのですが、そのネガティブを完全に活かすためには、完全な収縮が必要なんです。その収縮は、スピードがついた動作では生まれません。スピードをつけると(反動で)すぐに伸びてしまいますから。つまり、筋肉をしっかりと収縮させきれないような重量ではネガティブは十分に活かしきれません。完全に収縮させるという感覚を身につけて、そこから無理やり筋肉を引き伸ばしていくようなイメージです。これが出来ないと、結局は重量を扱っているけどもいつまで経っても進歩がないということにもなりかねません。
――そして昨年10月には「GYM SUE」がオープンし、そうした須江選手の技術に触れられる場が誕生しました。以前から、いつか自分のジムを持ちたいという思いはあったのでしょうか。
須江 ありました。ただ、なかなか踏ん切りはつきませんでした。やはり公務員を続けていれば安定というものは得られるわけで、そうした生活を投げ捨ててしまうには相応の勇気が必要だったのです。しかし、踏み出してみないことには何も始まりません。
これが正しい選択だったのかどうかまだ分かりませんが、自分の意思で決めたことには変わりありません。やらずに後悔するのと、実際にやってみて後悔するのとではどちらがいいか。そう考えた時に、やらずに後悔するようなことはしたくないと思いました。
――今、若い選手たちがこのジムを訪ねてきます。須江選手自身、「やってよかった」と思えることも増えてきたのではないでしょうか。
須江 毎日ありがたみを感じながら取り組めます。自分で探してここに来てくれた方々には、私も真剣に向き合わなければいけません。一人ひとりの方と本気で向き合える時間があるということに幸せを感じています。
――お話を伺っていると、ボディビルは個人競技ですが、いろんな人たちの支えがあってこそのものだということを感じます。
須江 そうなんです。このジムに来てくれる若い世代の人たちにも言っているのですが、一人でやれることには限りがあります。どれだけ多くの人に支えられているか、それに気づけないようなら選手として大成しません。一生懸命やっている人には手助けしてあげたくなるものです。手助けしてくれるんだったら喜んでそれをありがたく受け入れればいい。中途半端な頑張りでは、そのようにはなれませんから。支えて貰えるような選手になってほしいと。
――昨年は20代の選手たちの活躍も目立ちました。「なにくそ!」「まだまだ負けてられない」という思いは?
須江 いえ、これまで築いてきたものの上であぐらをかいているようではいけないと思っています。若い選手とも対等な立場で、本気で向き合って戦う。それが楽しいんです。親子以上の年の差があるような選手たちと戦うようになってきたわけですが、これは他の競技ではあり得ないことです。そういった意味でもボディビルという競技と出会えたのは幸せなことだと思います。今ある最高の自分を作り出して披露したい。それだけです。
ボディビルは終わりのない競技です。例えば400mリレーでは、次の走者が全速力で走っていけるように、前の走者が全速力で走ってきてバトンを渡します。ボディビルの大会の当日というのは、未来に向けて走る自分が待機している場所なんです。そこに過去の自分が全速力で走っていって、未来に向けて全力で走ろうとしている自分にバトンを渡す。これが延々と続いていくんです。全速力で走って行かないと、全速力で走ろうとしている自分にバトンを渡せません。
――最後に、今後の選手としての目標をお願いします。
須江 自宅に妻からのプレゼントされた額があるんです。それはメダルを入れられるように型取りがされていて、「あなたは3位が多いから、そのメダルをこれに飾って」と。私は今までに3位が5回、2位が2回あります。その5回の3位のうちの1回は引退する前に獲得したもので、結婚してからは4回獲っています。そのメダルを1個ずつ額に入れられるようにしてくれたんですね。でも、あと1つだけ、穴が残っているんです。その穴にメダルを入れて、額を完成させたいです。
すえ・まさひろ
1967年2月27日生まれ、埼玉県出身。身長161cm体重70㎏(オン)77kg(オフ)学生選手権で2連覇を果たしてから現在まで、その象徴的な背中で“伝説”とまで称される日本屈指のボディビルダー。埼玉県東松山市に、昨年10月にオープンした自身のジム『GYM SUE』を構える。
主な戦績:
1988・1989年 全日本学生ボディビル選手権優勝
1993年 選抜70㎏級優勝
2006年 日本クラス別選手権75㎏級優勝
2008・2009年 日本選手権2位
執筆者:藤本かずまさ
IRONMAN等を中心にトレーニング系メディア、書籍で執筆・編集活動を展開中。好きな言葉は「血中アミノ酸濃度」「同化作用」。株式会社プッシュアップ代表。
須江正尋選手のおすすめ記事☟ 数多くのドラマが見られた昨年の日本選手権。選手たちはどのような思いで、あの日のあのステージに上がったのか。ここでは男子ボディビル、女子フィジークの各2位から12位までの選手を単独取材。感動の舞台裏に迫る。
取材:IRONMAN編集部 撮影:中島康介
2021年男子日本ボディビル...
数多くのドラマが見られた昨年の日本選手権。選手たちはどのような思いで、あの日のあのステージに上がったのか。ここでは男子ボディビル、女子フィジークの各2位から12位までの選手を単独取材。感動の舞台裏に迫る。
取材:IRONMAN編集部 撮影:中島康介
2021年男子日本ボディビル... 分厚く大きく広がった背中を持つ、須江正尋選手。昨年10月にオープンした通称〝須江ジム〞でのトレーニング、また、今後どのように活動していくかを語っていただいた。
取材・文:IM編集部 撮影:北岡一浩
――2019年の日本選手権後から、現在までのトレーニングで何か変わったことはありまし...
分厚く大きく広がった背中を持つ、須江正尋選手。昨年10月にオープンした通称〝須江ジム〞でのトレーニング、また、今後どのように活動していくかを語っていただいた。
取材・文:IM編集部 撮影:北岡一浩
――2019年の日本選手権後から、現在までのトレーニングで何か変わったことはありまし...